連携取組で育てたい人材とは
この取組が目指すのは、発達障害の幼児への確かな支援力と幼児教育に対する強い情熱鵜を身につけた、幼稚園教諭や保育士の養成です
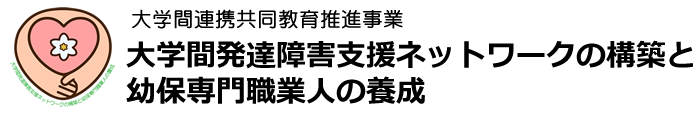
この取組が目指すのは、発達障害の幼児への確かな支援力と幼児教育に対する強い情熱鵜を身につけた、幼稚園教諭や保育士の養成です
佐賀県3歳児検診では、発達障害として療育や経過観察が必要な幼児の数が増えています。発達障害の幼児がニーズに合った支援を継続的に受けることができる体制づくりや人材養成が急務です
佐賀県の国私立5大学は放送大学佐賀学習センターとも共同し、大学間連携組織(「大学コンソーシアム佐賀」)をつくり、『住んでよかった街づくり』のための様々な取組を行っています。今回、大学間発達障害支援ネットワークを構築し、発達障害に関する大学間共通教育プログラムの開発と地域の療育ニーズに対応できる体制づくりを、各大学の強みを結集して進めます。
5年間の前半は主として共通教育プログラムや共通評価観点の開発・実施・改善、佐賀県療育機関と協同した、大学間連携による療育の実現、後半はこれらを継続しつつ、事業で得られた教育及び療育の成果を、全国学会や全国フォーラムの開催を通して広く発信し、また発達障害に関する幼稚園教諭や保育士の養成カリキュラム案を提案します。取組期間終了後も大学コンソーシアム佐賀の事業として継続して実施します
この取組では、新たに「子ども発達支援士」を、プログラム修了生に認定します。卒業後も職能形成を連携校がサポートすることが目的です。佐賀県では毎年三百名余りが幼稚園教諭や保育士の免許を取得しています。平成28年度以降、毎年百名程度がこの資格も取得できるようにする計画です。また、幼児の行動観察記録システムや検査器具の充実により「気づく力」― 支援の要となる力を、どの大学でも確実に養成できるようになります
連携校は発達障害に関する学生教育や支援活動に積極的に取り組んできました。今回の取組を通して、教育や支援を効率的に進めるため、学生履修カルテシステムや幼児療育カルテシステムを構築することで、学生の履修状況に合った指導や卒後指導、そして幼児への継続支援を、連携校が共同しスムーズに効果的に進めることができるようになります
事業最終年度の平成28年度以降、連携校の学生百名程度が「子ども発達支援士」の資格を取得して、卒業することを目指しています。それにより、佐賀県内外の多くの幼稚園や保育所で、発達障害の幼児が適切な支援を受けることができるよう全力で取組を進めます。 また、大学間連携により地域の療育活動の一翼を確実に担います